ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 内水面支場トップページ > 内水面支場のコンテンツ > 霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス14
ここから本文です。
更新日:2020年6月10日
霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス14
水生植物体の重要性
かつての霞ヶ浦・北浦の沿岸では抽水植物のヨシやマコモ、浮葉植物のアサザやヒシ、そして枕水植物のエビモやササバモといった豊富な水生植物がみられました。これらが生育する水中から陸上への変化に富んだ環境は、魚介類や昆虫、野鳥など多様多種な生物のすみかやエサ場として格好の場となるほか、湖水の浄化機能を有することから注目され始めています。
しかし、現在の霞ヶ浦・北浦の湖岸はコンクリート護岸にとって変わり、浅場は減少し水生植物か増えにくい状態となっています。
現在の湖岸と自然湖岸の模式図
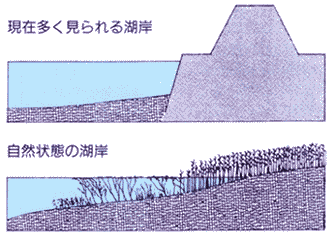
こういった状況の中で、湖から陸への「移行域」として水生植物帯が持つ、各種生物にとっての重要性や湖水の浄化能力について研究を行い、あわせて浄化能力の高い自然に近い形の水生植物帯を増やす方法を研究しています。
霞ヶ浦における抽水植物帯の面積の変化
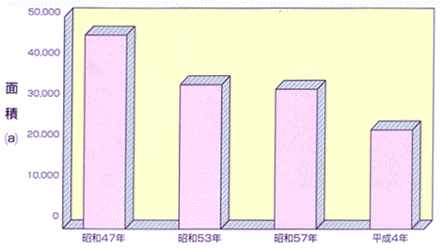
(昭和57年以前は桜井(1994)による。)現在は昭和47年の半分ほどになっています。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
