ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 内水面支場トップページ > 内水面支場のコンテンツ > 霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス12
ここから本文です。
更新日:2020年6月10日
霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス12
植物プランクトン相の変遷とその影響
昭和40年代なかば頃から50年代にかけて、夏場に多く発生したミクロキスティスを主体とする「アオコ」は、ところによっては風に吹き寄せられて厚く積み重なって腐敗し、ひどい臭いを発していました。
現在、ミクロキスティスの多い場所は入り江の奥部等ごくー部だけとなり、見た目には湖水がきれいになっているようにみえますが、別の種類の植物プランクトンの出現量が多くなり、汚れの程度を示すCOD値の低下はみられていません。
近年の霞ヶ浦湖心表層における主要な植物プランクトンの出現状況
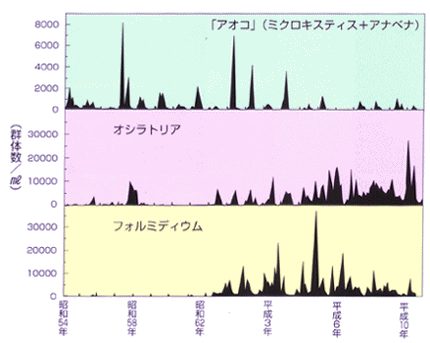
現在「アオコ」の発生量は少なく、代わってオシラトリアやフォルミディウムといった植物プランクトンが増えてきています。これらは夏だけでなく冬や春先にも増殖がみられますが、「アオコ」のように水面を覆うようなことはありません。
新しくみられるようになったものの中には、カビ臭さの原因となるものがあり、大きな問題となっています。また、このような植物プランクトン相の変化に伴って、光合成によるー次生産力の低下がみられることや、植物プランクトンの発生パターンに変化がみられることなどから、霞ヶ浦・北浦の生態系に変化が現れていることが推測されます。
このため、近年の漁獲量の急激な減少との関連について調査を行っています。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
