ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 内水面支場トップページ > 内水面支場のコンテンツ > 霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス9
ここから本文です。
更新日:2020年6月10日
霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス9
養殖負荷量を下げるための研究
近年、霞ヶ浦・北浦は、流域人口の増加や経済活動の活性化などにともない富栄養化が進行していることから、環境保全を図るためのさまざまな対策が講じられています。霞ヶ浦・北浦における窒素、リンなど栄養塩類の流入負荷源は、生活雑排水、工場排水、農地からの肥料の流入などさまざまですが、網いけすで養殖されているコイの排泄する尿、ふんも原因の一つとなっています。したがって、霞ヶ浦・北浦の環境を保全するため、湖を汚さない養殖技術の開発に取り組んでいます。
1.負荷量の少ない飼料の研究
たんぱく質は生物の細胞の主要な成分であり、工ネルギー源としても利用される非常に重要な栄養素です。このため魚を効率的に成長させるためには餌に含まれるたんぱく質の量をある程度増やす必要がありますが、飼料中のたんぱく質含有量を高めると、排泄物中のアンモニア態窒素量が増加します。
そこで、飼料中のたんぱく質含有量を抑える研究を行った結果、エネルギー源として使われるたんぱく質を脂肪に置き換えた、いわゆる低たんぱく高力ロリー飼料を開発し、餌料効率の改善、養殖魚の排泄窒素量の削減を可能にしました。この餌料の導入により昭和40年代には40%台であったたんぱく質含量が36%以下になりました。昭和58年以降、霞ヶ浦・北浦の網いけす養殖ではすべてこの改善飼料が使われています。
配合飼料の成分
| 従来の飼料 | 改善飼料 | |
| 昭和45年 | 平成6年 | |
| 粗たんぱく質 | 43.0% | 35.7% |
| 粗脂肪 | 3.4 | 9.2 |
| 灰分 | 11.0 | 10.0 |
| 水分 | 8.8 | 9.6 |
2.植物プランクトン食性の魚類の研究
ハクレン・へラブナは植物プランクトンを食べる魚です。これらは無給餌、あるいは少量の給餌という条件でも湖水中のプランクトンを捕食して成長するため、こうした魚種をコイに代えて網いけすに収容することにより湖内の窒素、リンの回収に寄与することができます。また、コイの生産量が減少するため、養殖負荷量の削減も併せて図られます。
ハクレン、ヘラブナのろ過水量およびプランクトン捕食量
| ハクレン | ヘラブナ(200gサイズ) | |
| ろ水量(l/キログラム・日) | 1,000 | 500 |
| プランクトン捕食量(g/キログラム・日) | 20 | 10 |
植物プランクトンの組成(乾燥)
| ミクロキスティス | アナベナ | シネドラ | メロシラ | |
| 炭素 | 48.5 | 46.3 | 23.5 | 16.6 |
| 窒素 | 9.9 | 9.6 | 2.9 | 2.3 |
| リン | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
夏期、プランクトン濃度20ppm(水中1リットル中に20ミリグラム(乾燥重量)のプランクトンが存在する濃度)で1キログラムのハクレンを飼育すると、1日当たり1,000リットル(=1トン)の水をろ過し、20gのプランクトンを捕食します。200gのヘラブナ5尾では、1日当たり500リットルの水をろ過し、10gのプランクトンを捕食します。
3.新たな養殖魚種の開発に関する研究
養殖魚は、一般に大きくなる魚ほど成長が速く、餌料効率もよくなる傾向にあることがわかっています。したがって、養殖負荷量を下げるためには大型化する魚を養殖魚種として導入することが望ましいといえます。また、コイよりも高価格で収益性の高い魚種も網いけすの収容量を減らすことができるため、負荷削減の有望な魚種といえます。
魚種別のふ化後日数と体重の関係
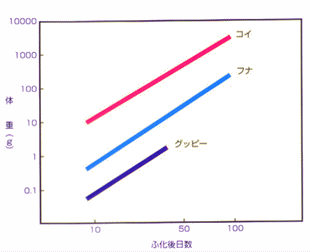
魚種別餌料効率
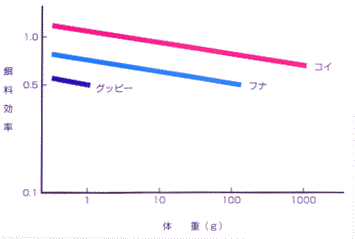
大型になる魚ほど、餌料効率がよいことがわかります。
餌料効率=成長量(体重増加量)/給餌量
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
