ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 内水面支場トップページ > 内水面支場のコンテンツ > 霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス1
ここから本文です。
更新日:2020年6月10日
霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス1
漁獲量の推移
霞ヶ浦・北浦の漁獲量は、昭和30年代まではワ力サギ・シラウオの漁獲が多く、ついでエビ・ハゼの順でした。昭和40年代になり総漁獲量が増加しましたが、ワカサギ・シラウオは減少し、エビ・ハゼが増加しました。
この理由としてはワカサギの漁獲方法が従来の帆びき網から効率のよいトロール漁へ転換したために、ワカサギの獲りすぎがおこりその資源量が減少したこと、ワカサギの減少によりこれと食う食われるの関係にあるエピ・ハゼにとって好適な条件を生み出したこと、そして富栄養化の進行が考えられています。
昭和50年代前半からは、ほとんどの魚種で漁獲量が減少しています。現在これらの原因として、植物プランクトン相の変化、水生植物帯の減少による産卵場や幼稚魚の隠れ場の減少等に着目して調査研究を進めています。
霞ヶ浦・北浦の漁獲量の推移
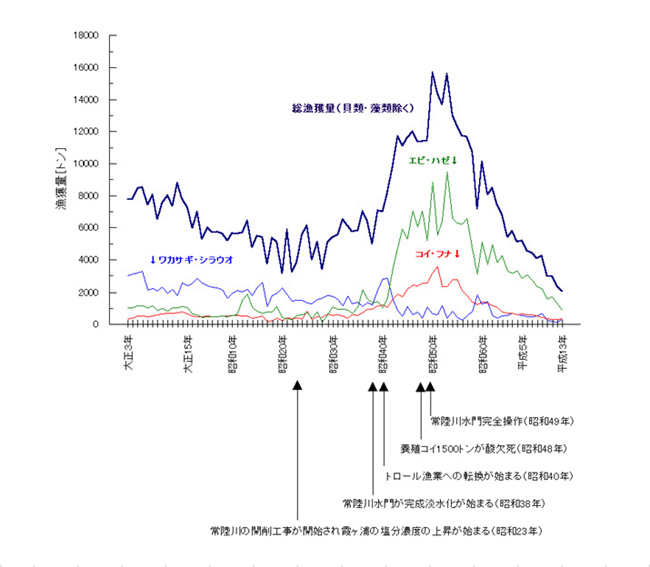
出典
霞北水産組合資料(大正3年~昭和23年)
水産振興場資料(昭和24年~昭和27年)
茨城農林水産統計年報(昭和28年~平成10年)
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
